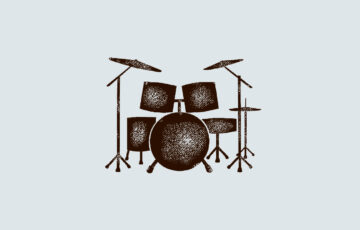こんにちは、野澤です。
個人的にバタバタしており気がつけば春が終わり梅雨も明けるくらい久々となりましたが、今回はウェイン・ショーターについての紹介とオススメアルバムをご紹介したいと思います。
ウェイン・ショーター(1933 – 2023)
レジェンドプレイヤーと呼ばれるほど著名な方ですが、近年まで長いキャリアを過ごされたサックス奏者です。
ニューヨークのすぐ隣のニュージャージ州に生まれ育ち16歳でクラリネットを始めましたがすぐにテナーサックスに楽器を変えました。
大学はニューヨーク大学の音楽科を卒業しその後軍隊に入った後、アートブレイキー&ザジャズメッセンジャーズの立ち上げにも関わったピアニストのホレスシルバーや、スタンケントンジャズオーケストラのメイナードファーガソンと演奏するなど少しずつ経験とキャリアを積み上げていきます。
ショーターが楽器を始めてから影響を受けたプレイヤーは1950年初頭の当時人気絶頂のソニーロリンズとジョンコルトレーン。
どちらもブリブリしたサウンドでタレント性があるプレイヤーを憧れにサックスを練習していました。
そのルーツもウェインの最初のアルバムから感じ取れますが彼には他にも別の才能がありプレイとその才能を開花させていきます。
その才能とは作曲センス。アートブレイキーに才能を見出され26歳の時にアートブレイキー&ジャズメッセンジャーズのメンバーに正式に加入します。
その特別な作曲センスを活かしメッセンジャーズに多くの曲を提供してバンドの方向性を大きく動かしていきました。
1960年にだしたメッセンジャーズのアルバムの「Like Someone In Love」は6曲中4曲がショーターの曲となっています。
加入したてのショーターにここまで任せているということはブレイキーはかなりショーターのことをかっていたのでしょう。
アートブレイキーのバンドで活躍することが約5年。この5年目の時にジャズの帝王と呼ばれるマイルス・ディビスがショーターに目をつけていたのでした。
ショーターの音楽人生がさらに大きく動いていくことになっていきます。
マイルスバンドでもその作曲センスを活かして多くの曲をバンドに提供しています。
「Sorcerer」ではマイルスがメンバーに作曲を任せたアルバムでもありますが7曲中4曲がショーターの曲となっていてマイルスも一目置いています。
マイルスが言うには「ウェインは本物の作曲者だ。彼は曲のスコアを全部書いて持ってきてメンバーに欲しいサウンドを細かく要求する。そしてショーターの曲は面白い要素を音楽のルールに持ち込むのが上手い。もしやってもらいたい要求をメンバーができなくてもショーターが音楽的センスを用いてうまく音楽をぶち壊していく。そのくらい音楽の中で自由になることができて音楽のルールを誰よりも理解している。」とマイルスは語っていたそうです。
言っていることの全てではないですがマイルスの言っていることはなんとなくわかるような気がします。
実際彼のアルバムとプレイを聴くと他のプレイヤーとは全然タイプが違うことがわかりますし後期のアルバムやライヴ映像を見ると自由に音楽をやっているのは誰の耳にも明らかです。
アートブレイキーのバンド以降はマイルのバンドをやりながらリーダーの活動にも力を入れていきます。
ハービーハンコックやリーモーガンなどの同世代ミュージシャンとの演奏を除くとサイドマンとしての演奏は少ないですね。今からはウェインショーターの音楽性について少し解説してみようと思います。
ウェインショーターの音楽性
ショーターの曲はどこかミステリアスな怪しい雰囲気を感じる曲が多いですね。
先ほど挙げたメッセンジャーズのアルバム「Like Someone In Love」の中の”Sleeping Dancer Sleep On”やメッセンジャーズでの同僚のトランペッターであるリーモーガンのアルバム「The Procrastinator」に収録されている”Dear Sir”では現実世界では感じられないような空気感がテーマで形作られています。
マイルスのアルバム「Nefertiti」のアルバム”Nefertiti”や”Fall”も同じ空気感を感じますがこちらの完成度はかなり高いです。
まだ聴いたことがない方はミステリアスなショーターの音楽性を知るにはぜひ聴いておきたいアルバムですね。
変化していくプレイスタイル
初期はコルトレーンのような音質だったりロリンズのようなフレーズ感を感じられます。
バップフレーズだったりモチーフだったりがとてもわかりやすいです。メッセンジャーズのアルバム全般的にそれが感じ取れますしショーターの初期のアルバムの「Introducing Wayne Shorter」や「Wayning Moments」はバップらしいフレーズが感じられます。
音色はこの頃からウェインらしい艶やかでローがよく混ざったテナーのサウンドがしています。
マイルスのバンドに入ると曲の怪しい雰囲気にマッチするようなプレイスタイルへ。
自分がメロディ楽器ではないのでうまくは言えませんが音使いやフレーズ感が初期の頃とは変わって独特な表現をしてくようになります。
リズムとしてははっきりとしたリズムを吹くタイプでモチーフもしっかり使っているのも特徴的です。
あまり音数で攻めるタイプではなく無駄のないフレーズでメンバーに音楽の行き先を指令しているかのような自由度も感じられます。
「Super Nova」あたりからソプラノサックスを使い始めてショーターのスタイルはここから凄まじく変化していくのです。
このアルバムから「Native Dancer」までの期間はアバンギャルドやフリーな感じでプレイスタイルも荒くなっていき感情的に吹く瞬間が増え始めてコルトレーンのような音楽の頂点を意識した音楽も取り入れ始めます。
同時期くらいにマイルスのアルバム「In A Silent Way」という時代を変えるアルバムに参加して新たなインスピレーションを受けて、同アルバムに参加したピアニストのジョーザヴィヌルと一緒にウェザーリポートというバンドを立ち上げます。
エレクトリックサウンドに特化したバンドで世界がフュージョン時代に突入するきっかけになるバンドの1つです。
リーダーアルバムとしては1985年の「Atlantis」では完全にフュージョンにシフトしてエレクトリックサウンドになります。
ウェザーリポートもそうですがコードは複雑化して1曲の情報量がとてつもなく多いです。
ここから「Phantom Navigater」,「Joy Rdier」,「High Life」とフュージョンまっしぐらなサウンドに。
ジャズ系のアドリブを重視するフレーズ感からポップスのような曲のメロディの延長線にあるようなソロへと変化してショーターの音数がより減っていきます。
「Alegria」からショーターの最後のバンドになります。ここからまたアコースティックなサウンドになりますが宇宙規模の音楽になっていきます。
冗談ではなくショーターは宇宙と繋がるために音楽をやっているというインタビューを見たことがありますが本当にこの世の音楽とは思えない壮大な音楽が展開されていきます。
ショーターはさらに音数が少なくなって周りのメンバーがすごいだけなのかと思いきやバンドサウンドをまとめているのはやはりショーターの音。
真似したくても誰も真似ができない境地に辿り着きました。
オススメのアルバム6選
ArtBlakey & the Jazz Messengers「Like Someone In Love」
このアルバムの頃からジャズメッセンジャーズでショーターの曲がフィーチャーされるようになってきました。
ショーターの初期の曲やプレイを感じたいかたはまずこのアルバムから入ってみるのもいいと思います。
このアルバムが気に入れば次に「Introducing Wayne Shorter」や「Buhaina’s Delight」などを聴いてみるのも良さそうです。
Wayne Shorter「Night Dreamer」
初期の頃から比べると少し洗練されショーターのミステリアスな部分がより現れたアルバムです。
メンバーはリー・モーガン(Trumpet)マッコイ・タイナー(Piano)レジー・ワークマン(Bass)エルビン・ジョーンズ(Drums)というメンバーでブルーノートのハードバップなサウンドも残っていますが”Oriental Folk Song”や”Virgo”など独特な空気感が漂います。
よくセッションで演奏される”Black Nile”もこちらがオリジナルテイク。
一度は聴いておいた方がいい1枚です。
これに近いショーターの音楽が感じられるのは「JUJU」や「Speak No Evil」といった作品になるのでこの2枚もオススメです。
Miles Davis「Nefertiti」
ジャズの帝王マイルス・デイビスの第2黄金期カルテット、とも呼ばれる、すばらしいメンバー編成のアルバム中、よく知られているのがネフェルティティ。
ウェインショーターはこの時期のマイルスバンドのメンバーでした。
1曲目はアルバムタイトルの曲でマイルスとショーターが繰り返しテーマのメロディをひたすら吹き、バックでリズムセクションが変化していくという珍しい楽曲です。
6分30秒ほどある楽曲ですが毎回違う雰囲気をリズム隊であるハービーハンコック、ロンカーター、トニーウィリアムズが作っていきます。
この発想もなかなかできませんがそのショーターのアイデアに応えるトニーウイリアムスもさすがです。
即興とは思えないほど1曲まるまる緻密なサウンドになっています。
終わりは決めてないのでフェードアウトのつもりでレコーディングしたと思いますが、最後まで録音を回していたのでエンディングはかなりぶつ切りで終わるのも、これはこれで面白いですね。
この頃のウェインに興味があれば「Sorcerer」や「
Weather Report 「Heavy Weather」
ウェザーリポートを結成して5,6年たったくらいのアルバムです。
“Birdland”や”Teen Town”,”Havona”など楽曲として聴きやすい曲が多いので最初はこのアルバムがオススメですね。
どれも曲全体の流れを意識した曲になっていて空間や間をみんなで共有しているのがわかります。
メロディはキャッチーですがそのあとはアドリブというよりコード進行の上で漂う感じのものが多いです。
“Havona”はクリスチャンマクブライドや最近だとDomi & JD Beckがカバーしていて最近の曲と言われてもわからないくらい新しいサウンドがする楽曲です。
この頃のショーターがハマればウェザーリポートの他のアルバム「Mr.Gone」を聴いてみてもいいかもしれません。
Wayne Shorter「Phantom Navigator」
フュージョン流行ど真ん中の時期のアルバムです。
今流行っているknowerやルイスコールのサウンドが好きならこのアルバムもハマるかもしれません。
同じようでありながら、ウェザーリポートとは違ってもう少しショーターのサウンドが楽曲の中心にあります。
ドラムのサウンドが打ち込みサウンドに近づいていてシンバルを逆再生する効果音も使われていたり当時のジャズのアルバムにしては斬新なアイデアを使ってレコーディングされています。
マイルスバンドの時のショーターしか知らない人からすると180度音楽性が違うアルバムになっているのでまずは聴いてみることをオススメします。
ハマれば「Atlantis」や「High Life」などもフュージョン系なので聴いてみると良さそうです。
Wayne Shorter「Beyond The Sound Barrier」
個人的にはこの時期のショーターバンドが一番好きです。
メンバーはダニーロペレス(Piano)ジョンパティトゥッチ(Bass)ブライアンブレイド(Drums)のカルテット。
曲という概念があるのかないのかわからないくらい即興的な演奏に従事していて、ずっと聴いていると常に素晴らしい音楽が展開されている空間を感じることになります。
同時に即興的だからこその緊張感も漂っていますが、迷いがある訳ではなく、演奏は自由そのものです。
ダニーロが作る静寂の中での美しいピアノの音、爆発的に盛り上がりをみせるブライアンのドラム、全体を俯瞰して流れをコントロールするジョンのベースのバランスが神がかっています。
何も考えずに聴けば、当たり前のように演奏して曲を終わらせているようにも感じますが、これだけすごい演奏になるというのは本人たちも予想以上らしくほぼ毎曲終わった後メンバーみんな興奮して声をあげています。
こんな風に白熱して演奏できる機会はそうそう無いでしょう。
少し前にダニーロペレス、ジョンパティトゥッチ、ブライアンブレイドのトリオでブルーノート東京で演奏をしており、アンコールにはウェインショーターの曲を演奏していました。
既にショーターは亡くなっていますが、この曲だけは一緒に演奏していたのではないかというくらい存在を感じることができ、彼が亡くなった後でも音楽がちゃんと受け継がれているのが伝わってウルッときましたね。
私としてはとてもオススメな1枚ですが興味があれば「Footprints Live!」や「Without Net」もぜひ聴いてほしいアルバムです。
最後に
ウェインショーターの音楽は一定のものではなく、時代と共に変化していきます。
ショーターの音楽が進化しているとも言えますが、どちらかというとショーターが時代に合わせて音楽を作り替えていっている印象も感じますね。
人前で演奏している多くのプレイヤーは、プレイスタイルを変えることがどれだけ大変かわかるでしょう。
それまでやってきたものから離れ、違うことに取り組むということはリスクもありますし既存のファンが離れていく可能性もあります。
しかしショーターは確実に時代の流れを読んで次世代の音楽を創っていきました。
今回ご紹介したアルバムを聴くだけでもウェインショーターという人物がプレイヤーとしてもコンポーザーとしても神がかっているのかがよくわかるのではないかと思います。
個人的には後期のバンドが気に入ってはいますが世代的にウェザーリポートが刺さる人、初期の王道なブルーノートサウンドが好きな人と大きく別れそうです。
あなたはどの時代のウェインショーターが好みでしょうか?色々聴いてみてお気に入りを探してみてください!