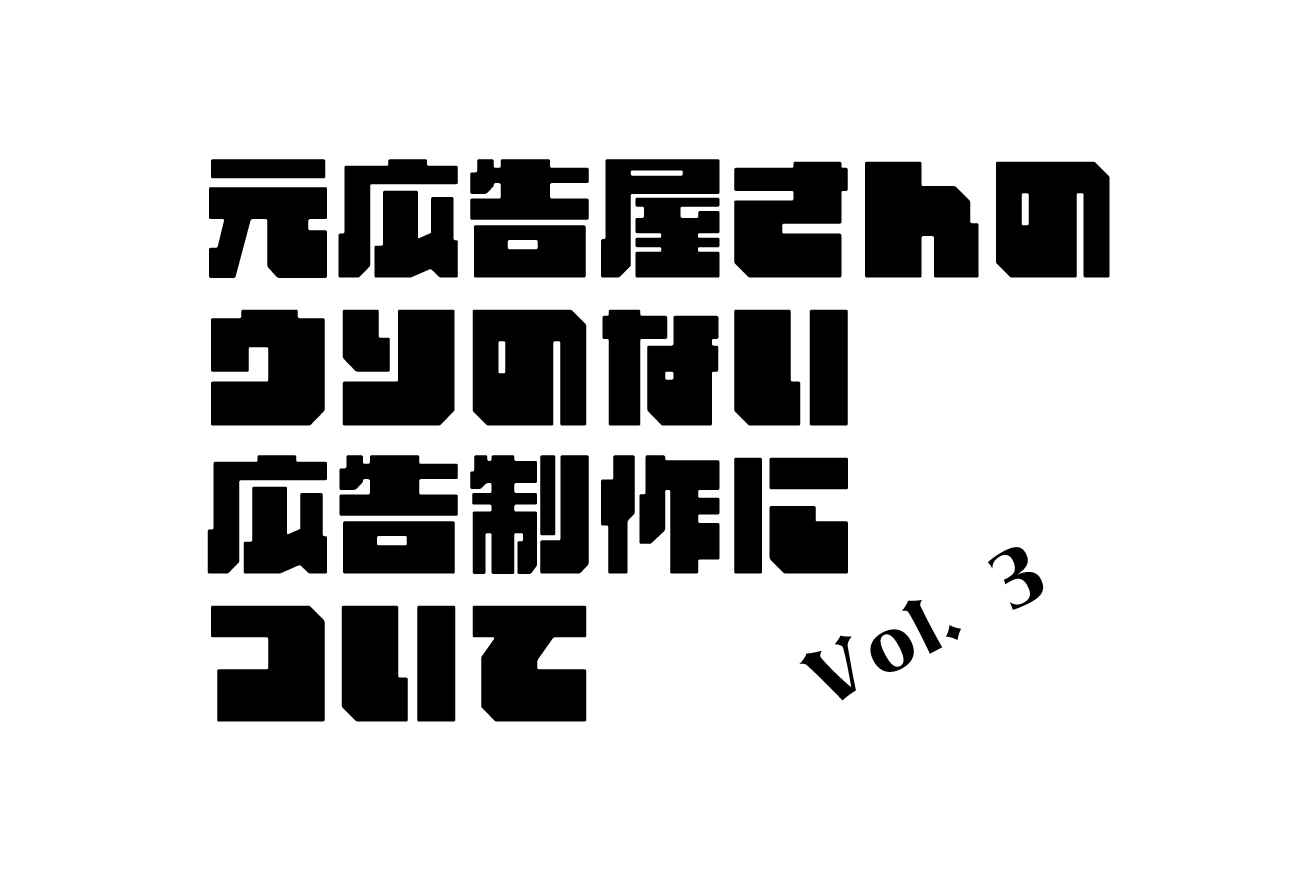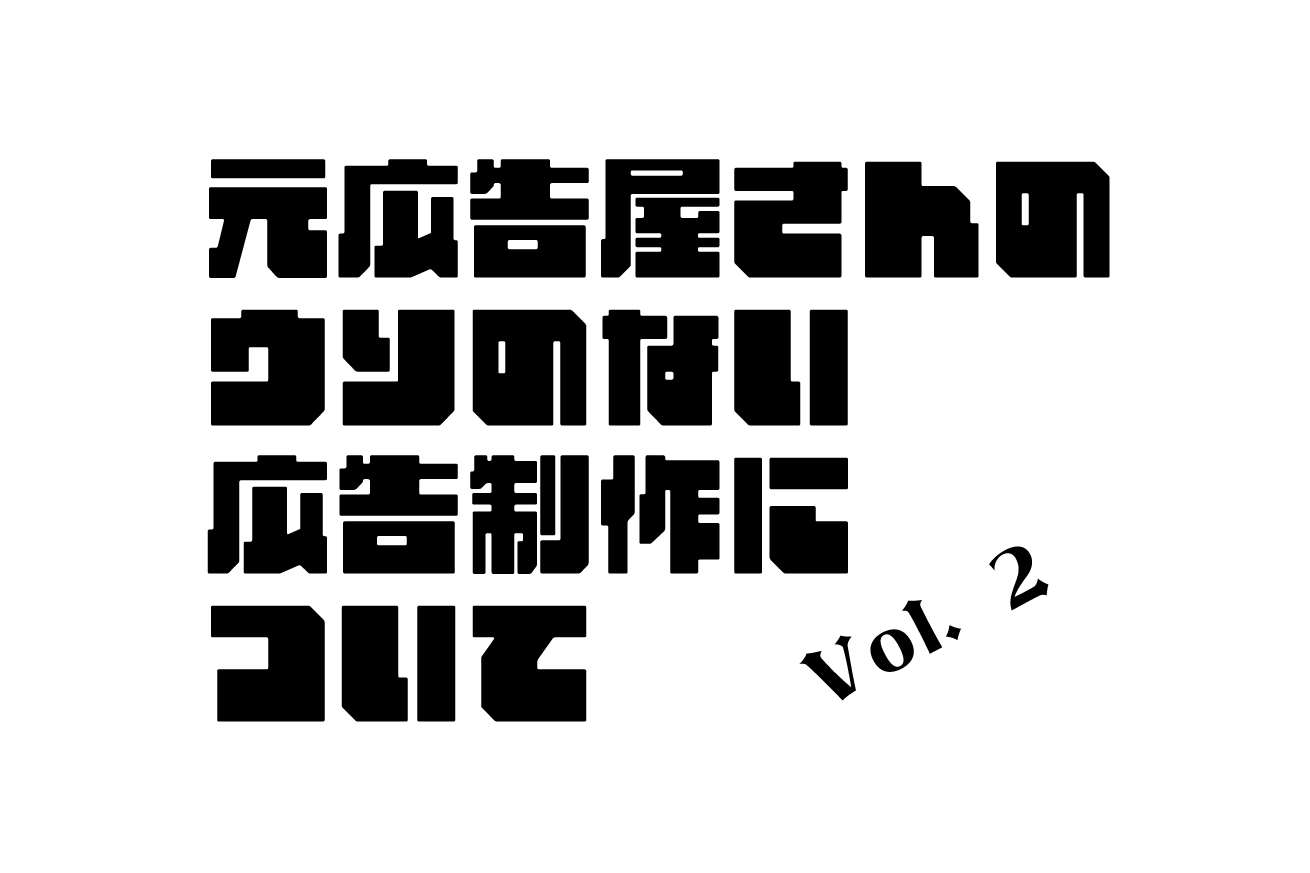今回は前回と違ってもっとコンテンポラリージャズに寄ったラージアンサンブルをご紹介します。
このアルバムが出た当時に聴き倒した思い出の1枚です。
ジェラルド・クレイトン「Life Forum」
パーソネル
- Gerald Clayton(piano)
- Joe Sanders(bass)
- Justin Brown(drums)
- Ambrose Akimusire(Trumpet)
- Dayna Stephens(Tenor Sax)
- Logan Richardson(Alto Sax)
- Gretchen Parlato (Vocal)
- Sachal Vasandani (Vocal)
- Carl Hancock Rux (poet)
アルバムトラック
- A Life Forum
- Future Reflection
- Shadmanthem
- Sir Third
- Deep Dry Ocean
- Dusk Baby
- Mao Nas Massa
- Prelude
- Some Always
- Like Water
- Unhidden
- When an Angel Sheds A Feather
- Skylark
メンバーはジェラルド・クレイトンのレギュラーのトリオに加えて同世代で活躍するホーンセクションとボーカル、それに語りが入った豪華編成になっています。
今までずっとトリオでアルバムを出して活動してきましたがこのアルバムから少し編成を大きくしました。
編成が大きくなることでジェラルドがやりたいと思っている音楽表現がさらに広がっているアルバムです。
アルバムのコンセプト
今回のこの「Life Forum」のコンセプトとしては仲間たちが自由に音楽で表現してもらえる場所をこのアルバムで作ったそうです。
立場関係なく自由に物事を言えるような場が現実世界でもできるようになったらいいという願いを込めて進めてきたアルバムでした。
メンバー選びからもお互い自由にできる人選になっていますし、メンバーもジェラルドがどういう風にしたいのか自然とキャッチできています。
ゴージャスに輝くコンテンポラリーサウンド
高級な食べ物を口に含んだ瞬間に美味しくて幸せと感じるようにこのアルバムは聴いた瞬間に耳が幸せになる音楽です。
コンテンポラリージャズ好きにはたまらないサウンドで、私なんかは聴いた瞬間から好きになってしまいました。
そもそもジェラルド・クレイトンのハーモニーセンスは素晴らしく、複雑な響きはするけれど大人で上品なサウンドがします。
それが今回ホーンセクションのアレンジによってもっとダイレクトに耳に伝わります。
ホーンの合間のコンピングや伴奏などでもジェラルドのセンスあるコードワークが聴けるので美味しいところだらけです。
2曲目にはグレッチェンの優しくも芯のあるボイスがホーンセクションに色づけされています。
難しいメロディなのにキャッチーな部分があってクセになりそうです。そういったメロディの複雑部分と聴きやすい部分を混ぜてバンド全体のサウンドをバランスよく仕上げています。
ラージアンサンブルとなるとクドい曲が多くなるものもあって途中で音楽を止めたりすることもありますが、このアルバムにはそういうこともなく最初から最後まで満足に聴けるアルバムです。
シンプルだけど魅力的な曲たち
この時代あたりからなんですが曲のテーマのメロディの感じや曲の長さが短くなったりしてシンプルになっていきました。
もう少し前をさかのぼるとカート・ローゼウィンケルやアダム・ロジャース、デイビッド・ビニーなどのコンテンポラリージャズは暗く複雑で一限様お断りな雰囲気があります。
↓一昔前のコンテンポラリージャズ
このアルバムの曲にはそういうコンテンポラリージャズの変なクセがなくシンプルです。ですが1曲1曲のキャラクターが良かったり、アルバム全体で聴くとストーリーがある曲が込められています。
1曲目では語りから始まりこのアルバムの紹介(イントロ)となる曲です。2曲目でバンドを引き立て、3曲目で落ち着いた雰囲気に持っていきます。
4曲目でまたスリルをくれる流れになってそこからまた落ち着いて6曲目に流れていきます。
一連の流れが良すぎてこの6曲目の「Dusk Baby」は心に染みる感動的な曲に感じます。
その後からはまた第2部といった感じで「Prelude」ではラジオで鳴ってるようなエフェクトから始まり、同じ曲調で「Some Always」が始まります。ここの流れもめっちゃオシャレです。
12曲目の「When an Angel Sheds a Feather」ではボーカルのグレッチェンとサッチャルの甘い歌声が味わえます。ジェラルドがミステリアスでキラキラしたサウンドをしていて、現実とは違うどこかに連れってってくれるかのような不思議な空間を持った曲です。
最後の「Ummg」はビリー・ストレイホーンの「Upper Manhattan Medical Group」の単語の頭文字をとっている替え歌曲です。曲もコード進行は「Upper Manhattan Medical Group」の進行をモチーフにしていてその上にオリジナルとは全く違ったメロディをのっけています。
最初は同じコード進行には聞こえにくいですがよく聴いていくとオリジナルに似ている瞬間がいくつかあります。
編成もテナーのダイナスティーブンス、ベースのジョーサンダースとジェラルドクレイトンという3人の編成で盛り上がる部分もありつつもスッキリとアルバム最後を締めくくります。
ライヴ並みに聴きごたえのあるソロ
インテリジェンスなジェラルドクレイトンのソロが楽しめるのはもちろんなんですが他のメンバーもぶっ飛んだソロを聴かせてくれます。
特にトランペットのアンブローズは変態的です。予期しない方向に音楽を持っていきます。
3曲目の「Shadmanthen」ではジェラルドのソロが終わるあたりからグルーヴが増してトランペットソロにつながるのですが、ピアノトリオが作っているハーモニーにわざとぶつかるような音を伸ばしてトランペットの音が入ってきます。
あまりにもその1音が強烈すぎてバンド全体に化学反応が起こっていきます。1音で空気を変えるアンブローズは本当に天才的です。
トランペットソロは終始不思議な感じですがその音遣いに対してジェラルドががっちりとハーモニーで応えてくれているので面白い展開へと音楽がどんどん広がっていきます。
10曲目の「Like Water」ではアルトのローガン・リチャードソンのソロが堪能できる曲です。
リズムはふわっとさせながら段々とバンドに混ざっていくようにソロが始まって優しく歌うようにソロを展開していきますがその時のサックスの音色に惹かれてしまいます。
段々と複雑なフレーズになっていきピアノはハーモニーで反応してドラムは細かいリズムで反応していきます。反応の仕方がアンサンブルとして面白いのでこれも聴きどころです。
このアルバムとしては曲を聴かせるというのが特徴なんですがしっかりソロの内容も充実しているのでアルバムを通して聴いててすごく満足感があります。
ラージアンサンブルでゴスペルミュージックを再現
ジェラルドは教会音楽であるゴスペルミュージックがバックボーンにあります。ドラムのジャスティン・ブラウンもルーツはゴスペルですね。
彼らだけでなく教会に行ってお祈りをして音楽をするというのがアメリカの文化としてあるので自然な流れなのかもしれません。
基本は大勢で歌ったり音楽をしたりするので今回はラージアンサンブルにすることによってゴスペルサウンドを現したかったのかなとこのアルバムを聴いて想像しました。
それかつくったものがたまたまゴスペルに寄ったのかもしれませんがやはりジェラルドのルーツが感じられます。
「A Life Forum」や「Some Always」はまさにチャーチミュージックな感じがオルガンサウンドから伝わります。
他にもグレッチェン、サッチェル、ローガンが優しいサウンドで音楽をつくっているのも祈りだったり愛だったりと教会に通じるものを感じますよね。
もちろんジャズとしての要素もたくさん含んでいるのでコンテンポラリージャズを素直に楽しめる1枚になってます。