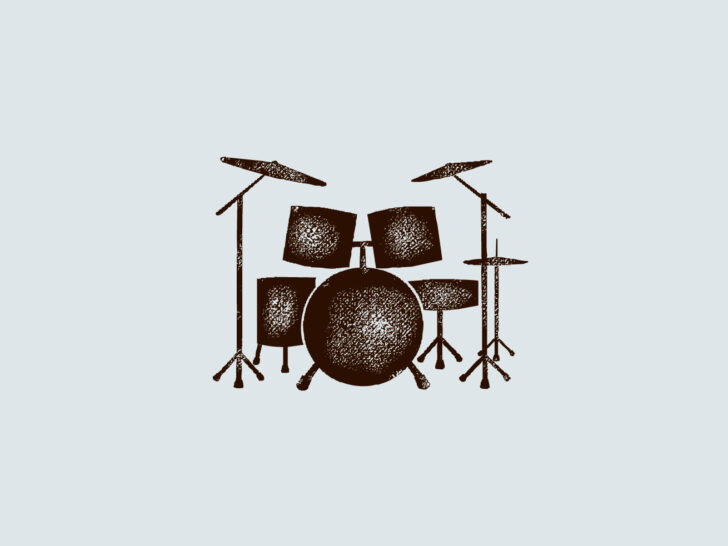こんにちは、野澤です。
2023年、大人気漫画のブルージャイアントが映画化されましたね。
これまでジャズに触れてこなかった方からも大きな反響があったようですが、ジャズ界隈的にもブルージャイアント熱は冷めやまず、プレイヤーや関係者と会う度にまだまだ熱い話題が挙がります。
実際ライヴに来られるお客さんもブルージャイアントからジャズにハマったという人もいるほどです。
私は最初、原作未読のままブルージャイアントの映画を観に行きましが思わず感動してしまいました。。
(ここから若干のネタバレあり。ストーリーの核心、というものではないですがネタバレ一切禁止の方はブラウザバックです!)
ドラマー目線で映画の共感できるポイントとしては初ライブシーンで曲の途中でドラマーの玉田がロスト(曲中のどこを演奏しているのか分からなくなってしまうこと)して演奏が止まってしまうところ。
これは自分も経験したことがあるので、見ていて心臓に悪かったです。
ピアニストのユキノリがソーブルーの支配人にダメ出しされるのも、つい感情が入り込んで見てしまい、まるで自分が言われているかのような気分でした笑。
他にも感動したポイントなどもたくさんありますが、これ以上はクリティカルなネタバレになってしまうのでここまでにしておきます。
さて、そんな話題にことかかないブルージャイアントですが、肝心の主人公について。
音楽性の軸は演奏シーンで流れる音を聴いただけで誰をイメージしているかすぐにわかりました。
きっと主人公の宮本大はジョン・コルトレーンに憧れているという設定なのでしょう。
実際その後原作を読んでみるとコルトレーンを意識しているシーンがあってやっぱりそうなんだなと確信しました。
そんなブルージャイアントの根幹にかかるかもしれない、ジャズレジェンドのテナーサックス奏者ジョン・コルトレーンについて。
ブルージャイアントファンでも、一度は聞いていたほうがいいかもしれませんよ。
ジョン・コルトレーン(Tenor Sax) 1926-1967年
コルトレーンはノースカロライナで生まれ育ち、高校生のときにはクラリネットとアルトサックスを演奏していました。
しばらくはそのまま演奏していたようですが、当時の人気サックスプレイヤーであるレスター・ヤングやジョニー・ホッジスの演奏を聴いて感銘を受けたのか、楽器をテナーサックスに変えます。
高校を卒業した後は軍隊の訓練に従事するために休む時期もありましたが、フィラデルフィアにて演奏活動を始めこれまた当時人気のサックスプレイヤーであるジミー・ヒースのバンドに参加するなど経験値を積みながら現地での知名度を上げていきます。
コルトレーンがその名を業界に轟かせるのはもう少し後で、21歳のときに今や伝説的なトランペットプレイヤーとなったマイルス・ディビスのバンドに加入したことで一気に名前が知れていきました。
その後マイルスのバンドでアルバム制作にも参加するなど、当時すでにジャズの帝王として君臨していた名プレイヤーのバンド活動を通して着実な成長を遂げていきます。
また、こちらも現在では伝説的な名声を誇るピアニストのセロニアス・モンクのバンドにも参加し、ここでも演奏的にも人間的にも大きな成長を遂げました。
ジャズの教科書に載るようなプレイヤーのバンドにばかり参加していますが、ここまではまだ若手のいいプレイヤーという印象の演奏とも言えます(それでも後の名プレイヤーたちに才能を見出されているともとれますね)。
コルトレーン独自の手法を手に入れたのはモンクのバンド参加以降。
詳しくは後述しますが、さまざまな経験を通して彼独自の演奏スタイルを創り上げ、現代のサックスプレイヤーもいやいやながら(笑)一度は通る道、コルトレーンチェンジを完成させます。
コルトレーンの演奏スタイル
コルトレーンチェンジの前に聴き比べて欲しいのが初期の頃と後期の頃の違いです。
マイルスバンドに参加し出した初期の頃は音楽的スペースを使いながらバップフレーズを駆使していてトーンは艶がありながら落ち着いています。
1956年発表のマイルスのアルバム「Round About Midnight」では上記のようなプレイが聴けますね。
マイルスは自身がトランペットを吹きまくって音数多く演奏するタイプではありません。
現代でも同じスタイルのプレイヤーは横に盛り上げ役としてのサックスプレイヤーを欲しますが、このときもコルトレーンにそういった役割を任せようとしていたのでしょう。
今も残る当時のマイルスの印象を学ぶと、きっと多くを語らなかったと思いますがコルトレーンはそれを察知して自身のプレイスタイルをだんだんと変化させていっていたように感じます。
マイルスのバンドに参加したのは数年間のみですが所属中にどんどんスタイルが変わっていき、1958年に発表されたマイルスの「Milestones」というアルバムでは、なめらかなフレーズ感ですがアグレッシブに吹きまくるプレイスタイルになっています。
空間をサックスの音で敷き詰めるようにも聞こえて、後にその演奏スタイルを”シーツオブサウンド”と名付ける人も現れました。
そして、コルトレーンが自身のバンドで活動するようになる前後に、音楽的なストイックさを発露した演奏方法を産みだします。
彼自身の理論を持ってコードチェンジの開拓をしていき3小節の間で3回転調する3トニックシステム、通称「コルトレーンチェンジ」というコードチェンジを編み出しました。
私はドラマーなのでその大変さを完全には理解していませんが、プロのプレイヤーでも相当苦労するコードチェンジが入っていることはジャズプレイヤーやコアなファンの方ならご存知でしょう。
アルバムでもありタイトル曲でもある代表作の1つ「Giant Steps」にもこのコルトレーンチェンジが使われています。
このアルバムにはピアノにトミー・フラナガンというデトロイト出身の実力派ミュージシャンが参加していますが、彼でさえアルバム中においてちゃんと弾けていないので、やはり相当難しかったのだと思います。
(余談ですが、その後トミー・フラナガンは自身のアルバムで「Giant Steps」を取り上げてリベンジレコーディングしています笑。この新しい演奏方法に対応できなかったのがよほどくやしかったのでしょう。)
それではこのコルトレーンチェンジをずっと使用していったのかというとそうはならず、「Giant Steps」以降には今度はコードに縛られないモードジャズの世界へ向かっていきます(モードジャズについて詳しくはこちらから)。
他プレイヤーのように自由に音を出して楽しむよりも、研究しきった新たな理論でガチガチに縛りをつけ、自分のプレイ、また自分自身を追い込むようなスタイルであったのに、正反対ともとれるような魂の叫びを表現するごとく自由に演奏するフリーに転換していき今までのスタイルをガラッと変えていく。
コルトレーンについて音楽的ストイックという表現を使いましたが、この言葉よりも的確な印象が思いつきません。
エネルギッシュな最強バンドメンバー
演奏方法からバンド構成の話に切り替えます。
アルバムを収録し始めた初期の頃はマイルスバンドで一緒だったベースのポール・チェンバースや、ドラムのフィリー・ジョー・ジョーンズまたはアート・テイラーと一緒にアルバムを作っていました。
今聞く限り、この頃はマイルスのようなバンドサウンドをイメージしていたと思います。
マイルスよろしく、コルトレーンがしっかりサウンドのセンターになるような作りにはなっていますが、マイルスよりも少し前に主流であった手法、バップがテクニカルな部分の軸になっていますね。
その後コルトレーンチェンジを始め、本人のやりたい方向が定まりバップから乖離していく際にピアノのマッコイ・タイナーとドラムのエルビン・ジョーンズがバンドに加わります。
少しずつ旧来の感覚のみを持つプレイヤーではついていけなくなってきたのでしょう。
そこでできた名作が「My Favorite Things」というアルバムです。
ベースはレジー・ワークマンが加わったカルテットで、しばらくはこのメンバーで演奏していました。
しかしレジーからエルビンとの相性がよいジミー・ギャリソンに代わり「Live At Birdland」というアルバム以降、マッコイ・タイナー(Piano)、ジミー・ギャリソン(Bass)、エルビン・ジョーンズ(Drums)との4人組、カルテットでの演奏をレギュラーとして活動していきます。
このカルテットで演奏している“My Favorite Things”は映像が残っているのですが、滝のような汗をダラダラと流しながら熱い演奏を延々と繰り広げていて、後半にはメンバーから文字通り湯気があがります。
ジャズファンであれば垂涎ものですので、見る機会がある人はぜひ楽しんでください。
マッコイのガツンとくるリズムで煽るようなコードワーク、地を這うようなローが響くジミーのベース、大波のようにうねるリズムを作り出すエルビンのドラム。
最強にグルーヴして勢いがあるサウンドの上でコルトレーンのシーツオブサウンドが炸裂します。
これが1曲20分という長さでテンション的にもいけるとこまでいってしまう(当時のジャズの演奏の中でもわりと長い方です)、プレイヤーとしての膨大なエネルギーが詰まった演奏を繰り広げられる様は胸熱です。
あまり聞き馴染みがない方だとフリーに、自由に演奏していてどこか破壊的に聞こえてしまうかもしれませんが、バンドのコードがしっかり聞こえてグルーヴもあるので全体的な曲の原型はとどめています。
魂を揺さぶるようなエネルギーのあるコルトレーンサウンド、そこからブルージャイアントもインスパイアされているのだと思います。
コルトレーンを聴くならこのアルバムがオススメ
1.「Blue Train」
コルトレーンを初めて聴くという方はまずこれを聴いてみてはいかがでしょうか。ジャケットも青く、アルバムタイトルとかけているのも印象的な一枚です(ちなみにジャケットデザインはリードマイルスというジャズ界でも著名なデザイナーが担当)。
コルトレーンのスタイルの中でも一番わかりやすい作品で、高音を吹くときの伸びやかな音や、たたみ掛けるような勢いのあるフレーズで聴きごたえのあるアルバムです。
トランペットのリー・モーガンもかなり勢いがあってコルトレーンに負けない音圧があります。
特に”Moment’s Notice”でのソロは秀逸です。
2.「My Favorite Things」
表題曲にブロードウェイミュージカルで一世を風靡したサウンドオブミュージックで使われていた劇中歌を選曲したこともあり、大ヒットしました。
日本でも「そうだ、京都へ行こう」のセリフが印象的なCMでお馴染みでしたね。
コルトレーン版では爽やかな感じではなく、シリアスで重々しいイントロからテーマに入っていきます。
このテイクではベースがスティーブ・ディビスの時代でジミー・ギャリソンのような激しい演奏ではないのですが、それでもコルトレーンのテンションがどんどん高まっていくのが感じられる1枚です。
このアルバムではコルトレーンがソプラノサックスを4曲中2曲吹いています。相当ソプラノサックスにハマっていた時代だったそうで、この後に出てくるプレイヤーたちはこのコルトレーンのソプラノに影響を受けています。
3.「Ballads」
コルトレーンといえば吹きまくるイメージを持たれがちですが、ゆったりとしたテンポであるバラードを演奏しても艶やかで感情に訴えかける表現の幅も広いのが驚きです。
この「幅」が、よくわかるのがこちら。
ソプラノもテナーも吹いていて1枚のアルバムでどちらの楽器も楽しめます。マイルスのようなリリカルな表現も感じられますね。
“I Wish I Knew”はテーマだけ吹いてソロはピアノに任せていますが、このテーマの歌い方も美しいです。
ピアノのマッコイ・タイナーもガンガンいくイメージが強いですがバラードを弾くと表現力が豊かなことで著名なピアニストであるデューク・エリントンのようなゴージャスなサウンドを奏でます。
落ち着いたアルバムですが”All Or Nathing At All”のようなラテンの曲も混じっていてアルバム全体で通して聴いても面白いです。
4.「Impressions」
ライブレコーディングしたものとスタジオでレコーディングしたものが混ざったアルバムです。
“Indiana”と “Impressions”はビレッジバンガードでライブレコーディングされたもので”Up Gainst Wall”は1962年の9月、”After the Rain”と”Dear Old Stockholm”は1963年の4月にルディ・ヴァン・ゲルダーのスタジオで録音したものです。
そのため基本はレギュラーカルテットのメンバーですが、メンバーもまちまちです。1曲目のベースはレジー・ワークマンが弾いて4,5曲目のドラムはロイ・ヘインズが叩いています。
これにベースクラリネットにエリック・ドルフィーが加わっています。
ドルフィーが加わることでフリー色が強まります。この人はコルトレーンのフリーっぽいプレイスタイルに大きな影響を与えた人物です。
演奏を聴いていても明らかに反応しあっているのでそこを聴いても面白いですね。
アルバムタイトルである”Impressions”は名曲です。エルビンのスイング感が超強力でスカッとするほど圧倒されます。ぜひチェックしてみましょう。
5.「Love Supreme」
コルトレーンといえばこれを避けることはできないでしょう。
オリジナル盤は4曲構成ですがクラシックの組曲みたいに全ての曲が繋がって1つの作品となっています。
聴くときはこのアルバムに込められたすべてを、覚悟して聴く感じになってしまいますがコルトレーンの演奏を真っ向から受けられる特別な作品です。
全員の演奏が曲として大事な役割を持っていてどのパートも責任が伴う曲ばかりです。
なのにどのメンバーもプレイが神がかっていて曲が持つポテンシャルを最大限に、いやコルトレーンが予想していた以上のものになっていると思います。
こういう作品に参加するには相当神経をすり減らしますが、それゆえ後世にも残る名盤として今でも聴き続けられています。
後期のコルトレーン
1965年以降はメンバーチェンジもしてフリージャズへ傾倒していきますが、このスタイルが当時はそこまで受け入れられず、それまでのファンは結構な数離れてコアなファンだけが残っていったとも言われています。
その後インドに渡りラヴィ・シャンカルというシタールのプレイヤーと共に演奏して仲を深めていきました。
そのラヴィとは相当深い関係だったので彼の名前をとって子どもにラヴィと名付けるほどでした。そのラヴィは今現在サックスプレイヤーとして活躍中です。
それからのコルトレーンの人生はそこまで長くはありませんでした。
亡くなるギリギリまで活動は続けていましたが、1967年には40歳という若さで癌により亡くなってしまいました。
年齢的には早すぎる最期でしたが、そのストイックな活動で残した音楽や精神性は現代ジャズ界にいまだにとてつもない影響を与えています。
モードジャズをマイルスとは違うアプローチで昇華させ、激しくグルーヴする中で吹き切る、とことんまでやり切ろうとするアスリート的な精神はコルトレーンならではのプレイスタイルです。
ここまでテクニックや理論だけでなくフリージャズを押し上げたプレイヤーは他にいないでしょう。
マイルスとは違うやり方で革新的なことをし、ビバップからハードバップ、フリージャズなどジャズの可能性を拡張したのもコルトレーンです。
そんなジョン・コルトレーン、話を聴くだけではもったいない。
ブルージャイアントの主人公のようにサックスの音に人生を変えらるのはいかがでしょう。