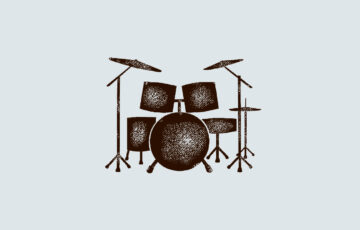神奈川県の西部にある小田原。
特産の海産物の1つにアジがありますが、最近は獲れる量が極端に少なく地元の食卓にもそんなに上がらなくなってきました。
肉厚で脂をたっぷり含み、刺身、たたき、焼き物、干物と食べ方にバリエーションも多いですが、アジは特産と言えどそこそこ値は張ります。
ちなみに小田原名物として一般的に販売されているアジの干物の多くは外国産の冷凍物のため、そこまで高くなく、また漁獲量の影響はあまりないようです。
さて、獲れないならば仕方ないのですが代わりに漁獲量が多くなったものがあります。

それが「じんた」。
アジの子供のことです。
じんたは地元での呼び名で、一般的には豆アジと呼ばれることが多いかもしれません。
ちなみにじんだ、と表記されることもあるようですが、そもそも字面で見ることがないので、じんたとじんだのどちらの呼び名が正しいのか分からないんですよね。
口伝えで聞いてきたものな上にじんたとじんだの発音が似すぎている。
ウチではじんたの方で通っています。
小田原ではかつては一般家庭でもよく食されてきましたが現在ではそうそう食べられません。
最近小田原に住み始めた人ではじんたという呼び名すら知られておらず、寂しいかぎりです。
先日お魚屋さんで聞いたら、こんなにじんたが獲れたことはないくらい。と言うほど水揚げされるようで、地球環境の変化を肌で感じます。
おおぶりの地物のアジとちがって、香りが抜群にいい、という訳ではなく、また脂のりも特筆するほどではなく。
ただしほかの小魚に比べると淡泊ながら皮の食感と風味がよく、このサイズでこんなに旨味が。といった印象。あるなら食べたい。と思わせてくれるお魚です。

さて、この量でも数百円。お安いです。
なので大家族なら大量に購入してじんたパーティーだ! と、するのはお気を付け下さい。
下処理しないとちょっと嫌味が残るから。調理にちょっと手間かかります。
じんたは小さいので唐揚げや天ぷらで食べられることが多いのですがこの手間を省くと味が二段は落ちます。
余談ですが、非常に腕のいいお魚屋さんなどではこれを一匹ずつひらいて干物にしていて、まるごとばりばりと食べられることもあります。
これが今みなさんが想像された以上においしいです。
干物にすると水分が抜けて味が濃縮されますが、そこまで成長していないからかクセがほとんどなく、いわゆるアジの干物とはまたちがった独特のうまみがあります。
が、最近は見かけることが少なくなりました。あれを干物にするのはかなりの労力ですからね。見つけたら買いです。まるごとバリバリ食べられるのでたくさん買っても大丈夫です。
下処理の話にもどります。
上記の「嫌味」ですが、ある処理をしていないと結構気になります。
それがエラと内臓を取り除いていない場合。
丸ごと食べる淡泊なお魚だからこそ、内臓とエラはちょっと嫌味を感じるんですよね。
そこで必要な下処理が「アゴをとる」こと。
アゴ、とはトビウオの呼び方の1つでもありますがそれとは違います。
これももしかすると小田原での地方独特の表現かもしれませんが、エラと内臓を手作業で取り除くことを指します。

魚体が極端に小さいので包丁は使いません。身もやわらかなのでペティナイフであってもぐずぐずにしてしまうことがあるので。
やり方はエラの中側に指を入れて…。

エラをつまんで引っ張り出して内臓も引き抜いてしまう壺抜き。

力はあまり入れないのがコツです。

できました。エラの外側もまるっと取ってしまいます。
これが「アゴをとる」という下処理です。

はい、作業完了。
だんだんと雑になっている様が見てとれる…。面倒なんですがね…。この一手間で味わいがガラリと変わるので…。

それから塩水を用意します。
濃度は1%いかないかくらい。身の柔らかな小魚は真水で洗うと味も極端に抜けるし身もゆるくなりすぎるので。
濃すぎるとかなり味が入るので海水と同じような3〜4%の濃度はいらないです。

まずは流水でほんとうにザッと血を洗い流して。

塩水にさらします。
漬ける、というよりはほかの作業の間一時的に置いておくためという感じでしょうか。
いくら塩水とはいえ、あまりさらしすぎると味はぐんぐん抜けていきます。
一応手で軽くかき回しながら魚体表面のぬめりも少しとります。
今回は唐揚げにします。天ぷらも嫌いではないのですが、そこはやはり青魚。
天ぷらって衣をつけて中の食材を蒸すように調理するので、どことなく匂いがこもってしまうんです。
むしろじんたのようなクセの少ない小魚だからこそ向いているかもしれませんが、個人的にはいずれにしろあまり好みではなく。
粉をうって唐揚げにするだけのほうがさっぱりと楽しめて好きです。

油の用意ができたらすぐにザルにあげてキッチンペーパーに包んで水分を軽めに除去。

そしてこちら。デュラムセモリナ粉に投入。
一般的な薄力粉よりも粒子も粗く小麦臭さが少ないのでオススメです。
本当にさっぱりした味わいになります。
ちなみに水を入れたり塩を入れたりしません。
表面の水分に粉をまとわせて揚げるだけ。さっき軽く塩水にさらしただけで味わいは十分。

こんな感じになったら粉を少しはたいて油に投入。
小さい魚なので160度くらい。

僕の手に水分が付いていてめちゃくちゃ跳ねました。熱かった…。
火が通りすぎるとすぐに消し炭になるので色づいたな、と思ったら気持ちもうすこし揚げて。

完成〜。
色づいた後にもう少しだけ揚げるのはアジにはぜいご、という固いウロコがあるから。
じんたくらい小さいとそこまで舌に触ることはないですが火の通しが甘いと少し歯に触るので。
ここをサクッとさせるのが揚げのコツです。ただし魚体の大きさはマチマチなので何分! みたいな目安がない。
慣れるしかないです。

では、いただきまーす。
うん、うまい。サクサクしているけれど中の身はすこしだけホロっとしていて。
塩がきつくないのでアジの風味を邪魔しません。
唐揚げよりもさっぱりとしているので結構な量お腹に入っちゃうんですよね。
僕は揚げ物にレモン搾らない派ですが、これは少しふりかけてもおいしい。
クセは油でかなり飛んでいるんですがやはりそこは青魚。レモンでうまみに感じるようにしてやるとさらにおいしい。

完全に忘れていましたがイタリアンパセリをかけるとさらにうまい。
ほぼ食べ終わってから思い出した…。
ちなみに乾燥もののイタパセは火を通さないとクセがあるので避けた方がいいです。フレッシュなものがオススメです。

では、再度。
うまい! これだけ小さくともしっかりと味わいのあるお魚もそうそうない。
そこにレモン、イタパセの風味。
抜群だ。お酒に合うよ。アペロールスプリッツァーのようなさわやかなやつで流し込みたいですね。
ということで、小田原名物じんたの唐揚げでした。
小さい魚体は活け締めなどができないので鮮度が命。
小田原在住の方はぜひ。観光で来た方には残念なお知らせですが、最近はお店で提供されることは稀で。
小田原ってこういう昔ながらの食材を扱うお店が他の観光地に比べて少ないんですよね。
小田原産の食材でない魚貝も結構多いです。
こういうの出してくれるお店をもしも見つけたら、ぜひ一度試されるのをオススメします。