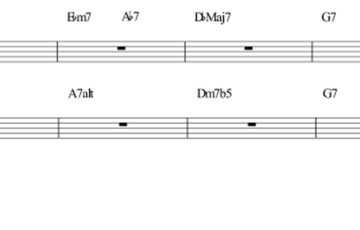ジャズを聴く人で、ニコラス・ペイトンというトランペッターをご存じない方はおそらく少ないはず。
1973年ニューオーリンズ生まれで、現在も活躍中のトランペッターです。
初期からウィントン・マルサリスやエルヴィン・ジョーンズなどに目をかけられ、さまざまなバンドで活躍してきました。
今回記事で取り上げるにあたって考えてみると、個人的には「ペイトンってこんな感じのトランペッターだよね」とはっきりと言い切ることができないトランペッターのような気がします。
ストレートアヘッドからヒップホップまで
その理由は、作品によって演奏スタイルが変わっていくからです。
傾向としては若い頃のものはニューオーリンズの雰囲気たっぷりの曲だったり、我々がジャムセッションで演奏するようなジャズスタンダードをよく取り上げていました。
ここまでだったらよくいる感じの超上手いトランペッターの典型なのですが、1999年のNick@Nightあたりから少しずつ様相が変わってきます。
この作品ではチェレスタやハープシコードが採用され、曲もオリジナルが中心となっていきます。
その後の作品では一作品ごとに作風というか、音楽のジャンルそのものが変わっていくという感じで、聴いている方は良い意味でついていくのが大変です(笑)。
全て紹介していたらきりがないので興味のある方は1999年以降の作品を順番に追ってみると良いでしょう。
Into The Blue以降
僕がトランペッターとしてのペイトンに大きな変化を感じたのは2008年発売のInto The Blueからです。
それ以前のペイトンと言えばファットで明るい音色でバリバリと吹きまくるイメージだったのですが、この作品以降は一言で言えば「枯れた」音色となり、吹きまくることはままあるにしても以前のような輝かしい印象は鳴りを潜めていきました。
また、Into The Blue以前ではアウトフレーズを多用しつつも丁寧で非常にわかりやすいフレージングが特徴だったのに対し、それ以降はやや複雑で抽象的なフレージングが顔をのぞかせることが増えてきます。
個人的には彼の若い頃の演奏はトランペッターとしては単純に気持ちよくて好きですし、アドリブを学ぶための教材としてもとても優れたものであると思います。
一方、近年のものは単にジャズトランペッターという枠にとらわれない芸術として、そしてペイトン自身のやりたいことをいかんなく表現することのできている(であろう)、とても優れたものであると思います。
余談ですが、近年ペイトンはトランペットと同時にピアノやフェンダーローズを演奏することが増えています。
いえ、鍵盤どころか歌ったりもするし、どこまで表現の幅を広げていくんだという気がします。
個人的にはあまり得意ではない分野ですがこんな作品も…。
かといって最新アルバムでは思いっきりスタンダード曲を取り上げてみたり…。
……いかがでしょう。
冒頭で「ペイトンってこんな感じのトランペッターだよね」とはっきりと言い切ることができないと書いたのも納得していただけるのではないでしょうか?
トランペッター目線からのオススメ作品
ニコラス・ペイトンというトランペッターの守備範囲の広さがよくお判りいただけたのではないかと思います。
ここからはトランペット奏者として僕が個人的に皆さんに聴いて欲しいペイトンの作品を挙げてみることにします。
かなり偏りはあるでしょうが、ただ聴いてみるだけでもよし、トランスクリプションの題材として利用するもよし、なセレクションになっていると思います。
#BAM: Live at Bohemian Caverns
この作品を聴くまでは比較的トラディショナルなスタイルを演奏するペイトンに慣れていたのですが、これを初めて聞いたときは度肝を抜かれました。
全然ジャズじゃないじゃん! と(笑)。
まあ別にジャズかどうかなんて音楽としては些末なこと。
僕と同じようにペイトン=トラディショナルなジャズというイメージを持っている人にはぜひ聴いていただきたい作品です。
もしかしたら音楽の表面を聴いた感じでは受け入れがたいかもしれませんが、きっと素晴らしい作品であると気づいてもらえるはずです。
Relaxin’ with Nick
今のところの最新アルバムです。
Smokeというマンハッタンの名門ジャズクラブでの演奏をレコーディングしたもので、ケニー・ワシントン(ds)、ピーター・ワシントン(b)という、Smokeでおなじみかつ強力なリズムセクションと共にトリオという編成での演奏です。
先にも書いたようにこの作品では彼にしては久しぶりのスタンダード曲がいくつか取り上げられており、今のペイトンがスタンダード曲を演奏したらこうなるのか! という驚きが得られるかと思います。
Fingerpainting: The Music of Herbie Hancock
奇しくもこちらもトリオによる作品です。
ただし1997年の作品で、ペイトンのキャリアの中では比較的初期に当たるものです。
ちなみに個人的にはペイトン作品の中では一番好きかもしれません。
こちらのメンバーはクリスチャン・マクブライド(b)とマーク・ホイットフィールド(gt)で、タイトルの通り、ハービー・ハンコックの曲を題材とした作品です。
ハンコックの曲ということで比較的難易度の高い曲ばかりなのですが、そんな曲たちをいともたやすく、針の穴を通すような限られたラインを通過しながら美しくメロディを紡いでいく様子はあっぱれです。
何を言っているのかわからない方は実際にトランスクライブしてみましょう。
美しい上によくできていて思わず唸ってしまうはずです。
Doc Cheatham & Nicholas Payton
こちらも上記作品と同じく1997年の作品。
レジェンドジャズトランペッター、ドク・チータムと共演している作品です。
レコーディング当時(1996年)恐らく90歳のチータムと24歳かそこらのペイトンとの共演……。
若かりし頃のペイトンの演奏が凄いのはもちろんのことですが、さすがはドク・チータム。
何がいいって、もう全てがいいとしか表現できない素晴らしい演奏です。
ぜひ実際に聴いてみてください。
それにしてもおじいちゃんと孫(下手したらひ孫か)という世代の共演。
ここまでの年齢差はさすがに珍しいですが、ジャムセッションなどでも僕の祖父母世代の方とも演奏する機会は決して珍しくありません。
親族以外では普段なかなか接しないような、世代の大きく離れた人とも演奏で盛り上がれる、こういったところもジャズの面白さですよね。