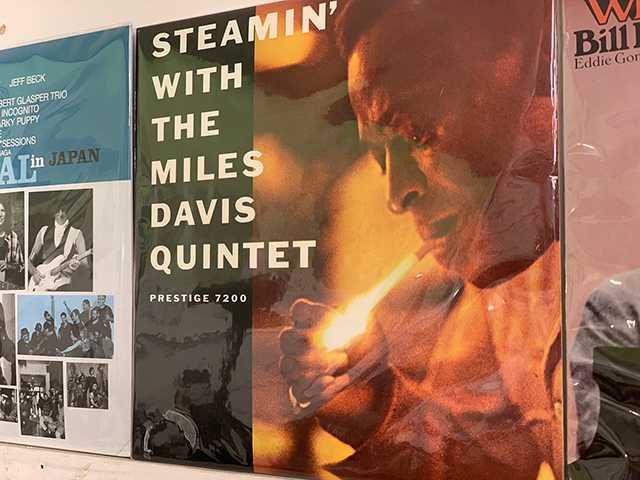前回はジャズの歴史上、最も偉大なトランペッターとは誰なのか、というタイトルでジャズの”帝王”マイルスデイビスに迫ってみましたが、今回はその続きです。
僕がマイルスこそ最も偉大なジャズトランペッターだと思う理由は大きく分けて2つあります。
マイルスだと分かるサウンド
当たり前じゃんって感じですが、少し聴けばマイルスだと分かるこの一目瞭然性は、芸術家として必要不可欠なものだと思います。
音楽に限らず、その人自身の個性よりも、その人が影響を受けた人の個性のほうがより際立っているアーティストはごまんと存在します。
とはいえ、既存の誰にも影響を受けずに独自の優れた芸術を作り出すことは不可能ではないにしろ、非常に困難です。
オリジナリティばかりを追求したところで芸術として、その質が低いものではただの自己満足の域を出ることはできません。
自分のことは最大限棚に上げさせてもらいますが、”オリジナリティ”に縛られるあまり一周回って”よくあるヤツ”で終わってしまってるアーティスト、よく見ません?(笑)。
芸術の質を上げるためには、やはり先人の真似をして優れたところを取り入れていくのが一般的であるわけですが、その結果として取り入れていったものに逆に支配されてしまうか、それともその中からオリジナリティを見出していくことができるかどうかがアーティストとしての命運を決定するような気がします。
マイルスサウンドの特徴
さて、マイルスといえばハーマンミュート(ワウワウミュートとも)を使った演奏は一般の方にも馴染み深いことでしょう。
それ以前にもディジーガレスピーなどもよくハーマンミュートを用いた演奏を行っていましたが、こんな風に違います。
どちらもマイナーキーの曲ですが、マイルスのほうがより暗くクールで押し殺したような印象を受けることかと思います。
今でこそ、こういったトランペットの演奏スタイルは珍しくありませんが、当時としては本当にマイルスだけのOne and Onlyと言っていいものでした。
もちろんミュートを外した状態(オープン)での演奏も当時の他のトランペッターと比較すると非常に個性的です。
ディジーガレスピー、クリフォードブラウン、フレディハバードなどのジャズの歴史に名を残す名トランペッターたちはトランペットという楽器を自由自在に操り、複雑なアドリブや素晴らしいテクニックを披露してきました。
しかし、マイルスは決してそういったスタイルの演奏をすることはありません。
例えば第二期クインテットより以前はダークな音色、歌うようなリリカルなフレージングで、決して音数が多い方ではありませんでしたし、なかでも初期のものは複雑なコードチェンジも知的なフレージングでスムーズに演奏しており、アドリブの教材としてもうってつけの演奏が多く見られます。
ここまでであれば、チェットベイカーやケニードーハムなども似たようなスタイルであったと言うことができますが、第二期クインテット以降はメロディをスムーズに繋げていくようなフレージングではなく、より抽象的な表現が増えていきます。
マイルスの演奏するフレージングだけを聴くとリリカルで口ずさみやすいものはかなり少なくなっていますし、この後の時代のものになるとその傾向はより強くなっていきます。
これは一体どういうことなのかを考えていくと、僕がマイルスこそ最も偉大なジャズトランペッターだと思う2つ目の理由に行き当たります。
1プレイヤーではなくバンドとしてのアンサンブルを重視
マイルスが現れる以前のジャズの演奏では、決してインタープレイが存在しなかったわけではありませんが、1人ひとりのプレイヤーがそれぞれの個人技を競わせたり、単にテーマやリフという単位によるアンサンブルの割合が多いものでした。
しかしマイルスが、明確に、自らのコンセプトを打ち出し始める第一期クインテット以降の演奏では、そういった演奏ではなく、バンドとしてのアンサンブルを非常に強く意識したものになっています。
例えば前回もご紹介した”Kind of Blue”を聴いてみてください。
1人ひとりのプレイヤー、例えばキャノンボール・アダレイやジョン・コルトレーンらの演奏は、彼らが自身のリーダーアルバムで見せる演奏とは異なり、かなり抑制されています。
彼らのような偉大なプレイヤーが本来見せるようなプレイではなく、むしろ抑制された演奏をしているのにもかかわらず、演奏全体としてみると非常に調和がとれています。
同じく第二期クインテットの演奏と、そのバンドからトランペットがマイルスからフレディ・ハバードへ入れ替わったバンド、(1976~79)ではアンサンブルとしてのまとまりが全く異なります。
もちろんこれだって素晴らしい演奏であることには間違いはなく、どちらが優れているかそうでないかという話でもないのですが、僕は第二期クインテット時代の演奏と比べるとトラディショナルな印象すら受けます。
ジャズのアンサンブルに引き算を持ち込んだ
バンドとしてのアンサンブルを重視する傾向が誰にでも分かるくらい顕在化するのは、個人的にはやはりこの第二期クインテット以降ではないかと思います。
それまでトランペッターは音を吹くことによって何かを主張しようとするのが当たり前でした。
そこに、マイルスは音を吹くだけでなく、敢えて吹かずに大きめのスペースを生むことによって、それまでのジャズバンドで行われてきたアンサンブルの自由度や色彩の幅を押し広げています。
クインテット(5人)による演奏だとして、従来のジャズの演奏が「1+1+1+1+1=5」だとするとマイルスのバンドは「1+1+1+1-1>5」を創りだしていたと言えば分かりやすいでしょうか。
アンサンブルに引き算を持ち込み、かえってアンサンブルが拡大していくという考え方は恐らくマイルスが初めてだったでしょうし、現代でもアンサンブルを行ううえでは非常に重視される観点です。
確かにぱっと聴いた感じだと上に挙げたVSOPによる演奏の方が第二期クインテットの演奏よりも先進的である印象を受ける方がほとんどでしょう。
しかし僕がこの演奏に”トラディショナル”な印象を受けると書いたのにはこういった理由があるのです。
叫ぶようなフレージング、音色
マイルスは第二期クインテット以降、単に音数を減らすだけでなく、これまで特徴的とされてきたリリカルなフレージングやその美しい音色すらも変化させていきます。
そもそもトランペッターがジャズをジャズらしく演奏するのならば、リリカルなフレージングや美しい音色は必須で、僕自身そのように教えています。
しかしマイルスが表現したいものの幅がより広がっていくにつれ、それまでのようにジャズをジャズという枠に当てはめて演奏することは、マイルスにとっては単なる障害となっていきました。
そこでマイルスの表現したい音楽に合わせて変化していったのが、口ずさみやすい、リリカルなフレージングや、いわゆるトランペッターとして美しいとされる音色です。
特にエレクトリック時代に入ってからはフレージングの抽象化と音色の変化はより顕著になっていきます。
それが分かりやすいのが”Agharta”(1975)というアルバム。
先に挙げたVSOPは1976年から活動を開始するバンドです。
好き嫌いはかなり分かれるところですが、マイルスがまさに時代の最先端を行っていたということだけは間違いないと言うことができるでしょう。
ある時点を境にジャズという枠組みを飛び出したマイルスですが、他のアーティストにありがちな単なる転向や鞍替えではなく、本人が表現したいものを突き詰めていったらそれがいつのまにかジャズとは呼ばれなくなっていったのだと僕は感じます。
ビバップ以降のジャズを開拓し、最後はそのジャズを突き破って晩年まで新たな境地を睨み続けたトランペッター、マイルスデイビス。
自らが表現したいもののためにはあらゆるものを(たとえそれがトランペッターとして必須だと言われるものであっても)大胆に変化させることを厭わない彼のその姿勢こそが本当の意味でジャズらしいのだと僕は思います。